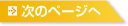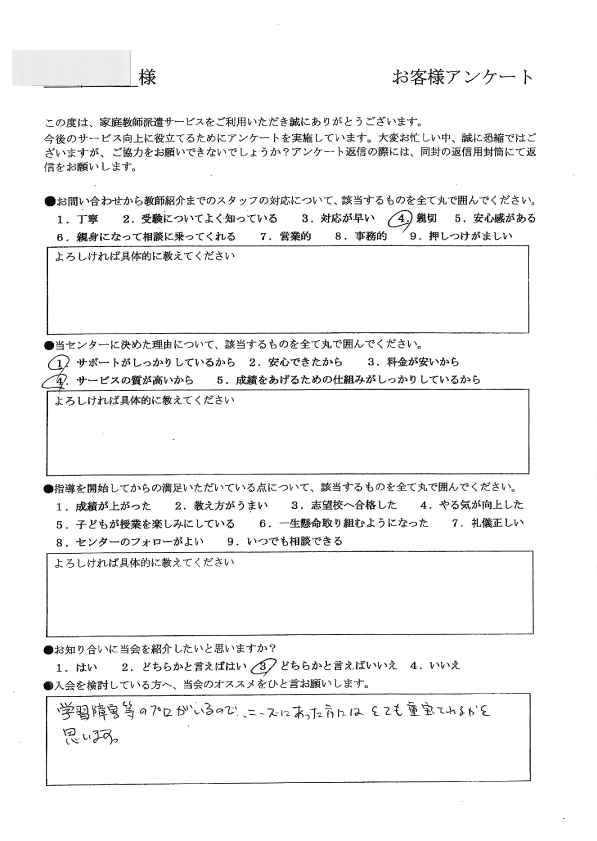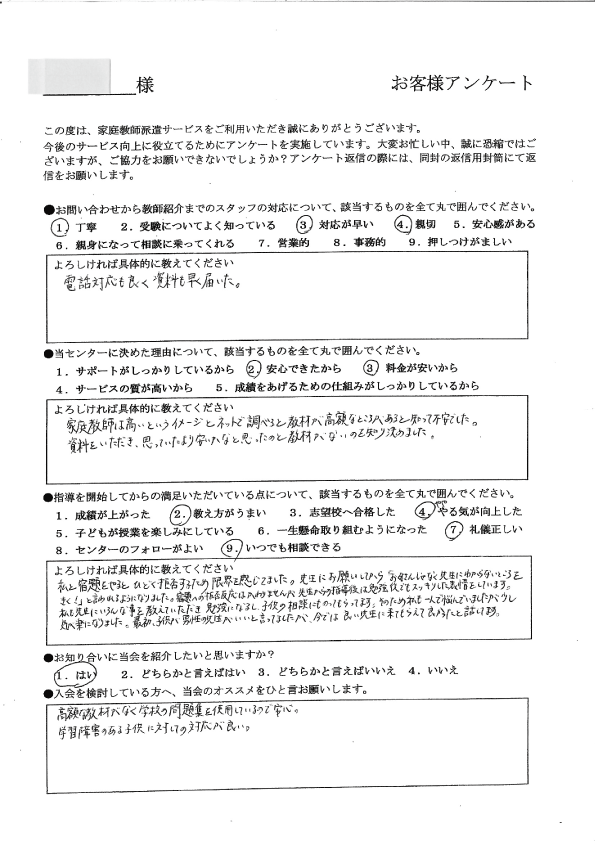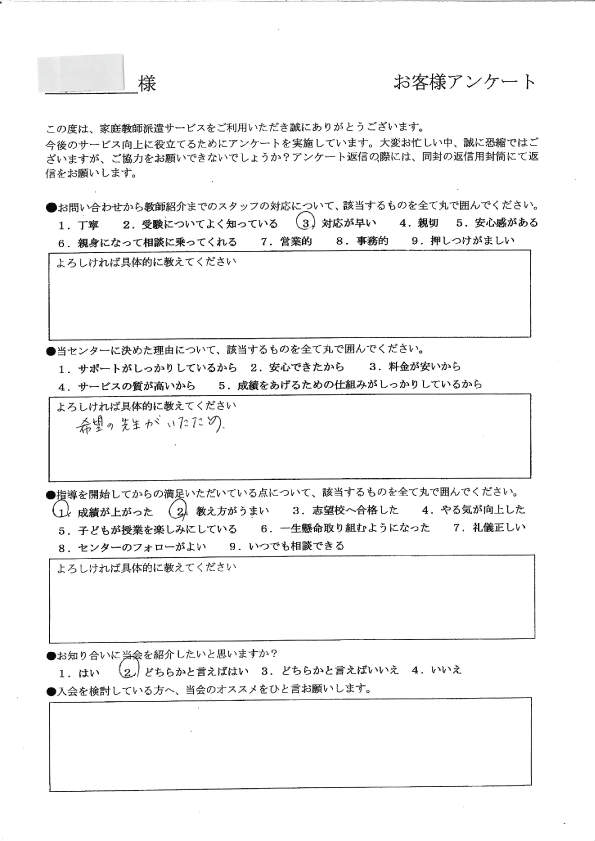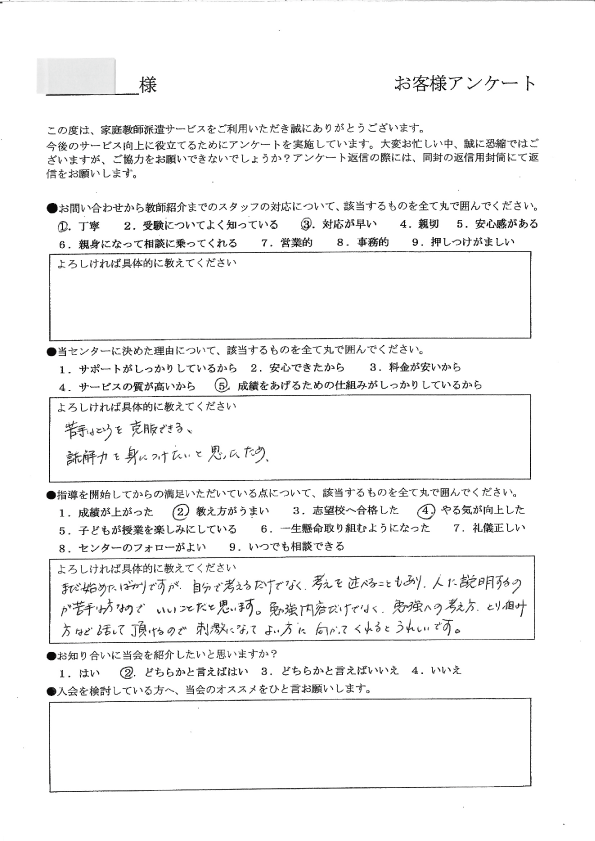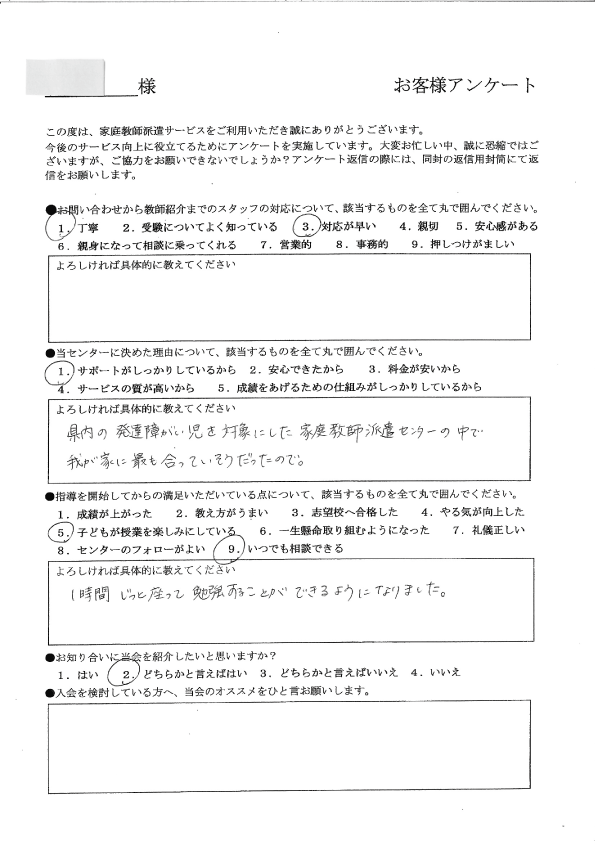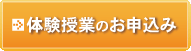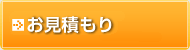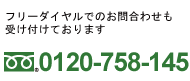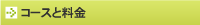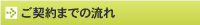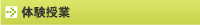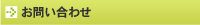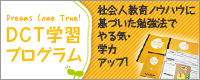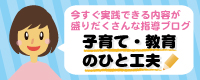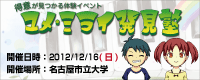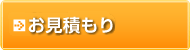せんせい通信10年02月号 PDFファイルはこちら
実践思考で考えて、指導の質を高めよう!
バンクーバーオリンピックが開催されています。オリンピックの選手たちは、4年に一度しかないこの大会で最高の結果が残せるように、毎日練習を積み重ねてきました。
練習をすると言っても、ただ闇雲にやっても結果はでません。オリンピックで最高の結果が残せるように毎日どのように過ごすかを緻密に計算し、日々の行動計画に落とし込みます。毎日何をやるかをまず決めてから行動するから結果が出ます。
家庭教師の現場でも同じ事が言えます。生徒とせっかく目標を決めても、日々の指導を事前にあまり考えずに流れに任せて行なっているだけでは結果がでることはほとんどありません。指導に行く前に毎回毎回、何をやるべきかを具体的に決めてから、指導に臨むことが大切です。ここで気をつけて欲しいのは、「数学をコツコツがんばる」「苦手を克服する」「弱点をなくす」というような抽象的な行動指針で終わってしまうことです。「数学をコツコツがんばる」「苦手を克服する」という抽象的な行動指針を基礎思考と言い、逆に、具体的に考えられた行動指針を実践思考と言います。基礎思考で考えただけで終わると、なかなか実際の行動に移すことができず、結果的に計画倒れとか目標を立てただけという状況に良く陥ります。「数学をがんばるって、一体何をがんばるんだ?」ってよくよく考えてみると気づくと思います。
基礎思考ではなく、「比例の問題の要点をまとめたメモを事前に準備して、それを活用して指導する」というように実践思考で考えることができると、考えたことを即行動に移すことができるため、目標達成の確率は格段に上昇します。
また、基礎思考を実践思考に切り換えるのは実は簡単です。基礎思考を達成するにはどのような行動をすればよいかを3回くらい自問自答すれば実践思考が浮かんできます。「数学をコツコツがんばる」という基礎思考なら、「○○は一次関数が苦手なんだよなぁ。特に、条件が複雑な文章題。文章題は、文章に書かれていることを絵や数式にすることが大切だから、、、。」と思慮を巡らし、「文章題を図解したものを準備して、文章題の解き方のコツを教えて、一次関数文章題の苦手を克服する」という実践思考が出てきます。是非、基礎思考ではなく実践思考で準備して指導をしてみて下さい。生徒の大きな変化が待っていると思います。
指導手帳をもっとうまく使いこなす術
指導手帳には、自分や生徒の気持ちも書くようにしてみてください。感情というのは、揮発性で時と共に薄れ、いずれは忘れてしまいます。例えば、試験に不合格になってすごく悔しい思いをして、2度とそんな思いをしないと決めて、はじめはがんばるのですが、その感覚は次第に薄れて、悔しさを忘れ、また同じ失敗をするということも起こります。
そのようなことを減らすための有効な手段が、気持ちも文字にして書き込むと言うことです。文字にすれば、それを読むとその時の感情を思い出すことができ、前回の指導の様子がより一層鮮明に蘇ってきます。そうすれば、今回の指導をどうしたらよいかという具体案も浮かびやすく、前回よりも質の高い指導を行なうことが可能になります。
ケースメソッド - 人のアイデアは役に立つ!
先生から頂いた改善点を元にケースを作成し、そのケースに対する対応策を頂いた改善策をベースに作成しました。そのため、複数の先生の意見が1つのケースとしてまとめられていることをご了承ください。
各ケースに対する対応策は、担当教師のつぶやきとして記載しました。他の先生が実践している対応策です。同じような改善点を抱えている先生は、是非自分に置き換えて、その対応策を実践してみてください。
ケース1:計算でケアレスミスがやたらと多い。そして、計算が遅い。
担当の先生のつぶやき(対応策)
計算が暗算でできることはよいことなんだけど、途中式を書かなさすぎなんだなぁ。これがネックになって、計算ミスを連発している気がするから、難易度が高い計算については、暗算をやめさせて、きちんと式を書かせるようにしてみよう。さらに正確に問題が解けるようになるためには、図やグラフを書かせることも大切。書くことを嫌がっているようだけど、粘り強く書くように働きかけ続けよう。最後はスピードだ。これは、やっぱり反復練習しかない。ルーティンで計算問題に取り組ませよう。
ケース2:英語力に難あり。単語、文法、構文力、全てが弱い。
担当の先生のつぶやき(対応策)
英単語がなかなか覚えられないようだ。単語力を身につけようと思ったら、何度も繰り返し書くことがまず大事だよな。あ、そうだ。五感をフルに使うとより覚えられると聞いたことがあるぞ。よし、音読もさせるようにしてみよう。単語は毎日ノートに書いてもらい、指導に行った時に小テストでチェックしよう。文法・構文の基本はまずSVOCだよな。中学生だとSVOCは習わないけど、教えてみよう。全ての英文の単語の下にS、Vなどを記入してもらって、文法について少しずつ説明していこう。
指導手帳ベストプラクティスの紹介
事例紹介:S.G先生の手帳
今回もたくさんの先生に指導手帳を提出していただきました。いつもありがとうございます。忙しくて、読んで添削することが億劫な気持ちになって、添削から少し逃げていたのですが、添削をはじめてみると、しっかりした内容の手帳が多くて、元気をたくさん頂けました。本当にありがとうございます。
今回は、G先生の手帳を紹介します。気持ちがたくさん書いてあって、生徒さんへの想いがビンビンに伝わってくる手帳でした。そして、その気持ちが、指導の工夫などの実践につながっていることに大変感心しました。
|
|
▼▼このページで紹介されている教師に直接指導を受けることも可能です▼▼

他の先生の紹介も見る
優秀な大学生教師
失敗から学ぶことが大事! 佐藤彩香先生(名古屋大学医学部)
夢の実現サポートします! 藤井淳喜先生(名古屋大学情報文化学部)
大変なのは、あなただけじゃない! 櫻井宙先生(名古屋大学工学部)
毎日のコツコツを大事にしよう! 榊原寛幸先生(名古屋大学工学部)
苦労した分だけ成長できる! 小林恭平先生(名古屋大学経済学部)
「どうしたらできるか」を考えよう 松永拓朗先生(岐阜大学工学部)
医学部の大学生教師
今日やるべきことはその日のうちに! 片岡龍司先生(名古屋大学医学部)
毎日少しでも机に向かうことが大事 星徹先生(岐阜大学医学部医学科)
経験豊富なプロ教師
勉強は日々の積重ねが大事! 久喜裕紀先生(慶應義塾大学卒)
家庭教師は生徒の味方 芦田千穂先生(お茶の水女子大学卒業)
受験合格はやる気と集中力! 野田奈保美先生(法政大学大学院卒)
よい環境がよい人間を育てる 渡邉士朗先生(ニューヨーク市立大学卒)